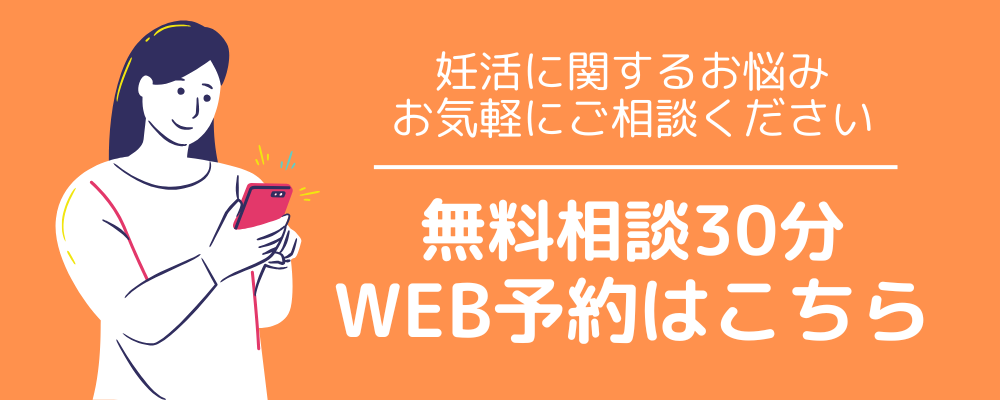「逆子」と診断されて不安を感じていませんか?
妊娠後期に胎児が頭を下にしていない状態を逆子(骨盤位)といいます。正期産(妊娠37週以降)ではおよそ3〜5%の確率で逆子となり、分娩時のリスクを避けるために帝王切開が検討されることがほとんどです。しかし、帝王切開は経腟分娩に比べてリスクが高く、できることなら避けたいと考える方も多いでしょう。
逆子はなぜ起こる?その原因と頻度
胎児は妊娠28週頃までに、子宮の中で頭を下にした「頭位(正常位)」で安定するのが一般的です。しかし、何らかの理由で逆子のまま安定してしまうと、分娩時に母子ともに危険な状態となる可能性があります。
逆子の頻度
- 妊娠28週未満: およそ30%
- 正期産(37週以降): およそ3〜5%
逆子が問題視されるのは、お腹の中で赤ちゃんが大きく成長し、回転するスペースが少なくなる妊娠28週を過ぎた頃からです。
逆子分娩のリスク
- 臍帯脱出: 胎児の足や臀部が先に産道に出てきた際に、へその緒が一緒に下がってしまい、赤ちゃんへの酸素供給が止まる危険性があります。
- 分娩遷延・難産: 胎児の頭部が産道で最も大きい部分であるため、頭から出ることでスムーズな分娩が期待できます。逆子の場合は、頭が最後に娩出されるため、分娩に時間がかかり難産になるリスクが高まります。
- 頭蓋内出血: 胎児の頭部が急激に娩出されることで、脳内に出血が起こる可能性があります。
こうしたリスクを避けるため、多くの産婦人科では、正期産を迎えても逆子の場合は、予定帝王切開が実施されます。
現代医学の逆子治療とその課題
逆子を治すための方法として、逆子体操や医師が手でお腹の外から赤ちゃんを回す外回転術などがありますが、これらの有効性は未だ明確にされていません。特に外回転術は、常位胎盤早期剥離や臍帯圧迫などのリスクがあるため、実施していない医師も多くいます。
東洋医学が考える逆子の原因と鍼灸治療
東洋医学では、逆子を「胎位不正」と呼び、身体の巡りやバランスの乱れが原因で起こると考えます。
逆子の3つの東洋医学的原因
- 気血両虚(きけつりょうきょ): 妊娠によって気と血(エネルギーと栄養)が不足し、胎児が自力で回転する力が弱まる状態。虚弱体質や慢性的な疲労感がある方に多いです。
- 気滞(きたい): ストレスや冷えによって気の巡りが滞り、胎児の回転が妨げられる状態。憂鬱な気分になりやすい、ため息が多い方に見られます。
- 脾虚(ひきょ): 脾臓(消化器系)の働きが弱く、体内の水分が停滞し、それが胎児の回転を阻害する状態。むくみやすい、身体が重だるい、食欲不振がある方に多いです。
鍼灸施術の開始時期
鍼灸での逆子治療は、妊娠20週から40週までの報告がありますが、28〜31週で治療を開始した方が回転率が高いという報告があります。赤ちゃんが大きくなりすぎる前に始めるのが効果的です。
古くから伝わる「至陰(しいん)」へのお灸
逆子治療には、足の小指の爪の生え際にある「至陰(しいん)」というツボへのお灸が古くから用いられてきました。このツボは、子宮の収縮を促す効果があると考えられていますが、その有効性のメカニズムはまだ解明されていません。
当院では、この至陰へのアプローチに加え、お一人おひとりの体質を見極め、全身のバランスを整える施術で、赤ちゃんが回転しやすい身体づくりをサポートします。
宇都宮鍼灸良導絡院の「マタニティ鍼灸」
当院では、妊活中の不妊鍼灸から、妊娠中のマタニティ鍼灸、出産後の骨盤矯正、そして二人目不妊まで、女性のライフステージに合わせた責任あるサポートを提供しています。
長年の実績で培った技術力と、日々進化する医学的情報を加味し、鍼灸というかたちであなたの妊娠・出産を全力で支えます。
「逆子」と診断された方も、ぜひ一度当院にご相談ください。