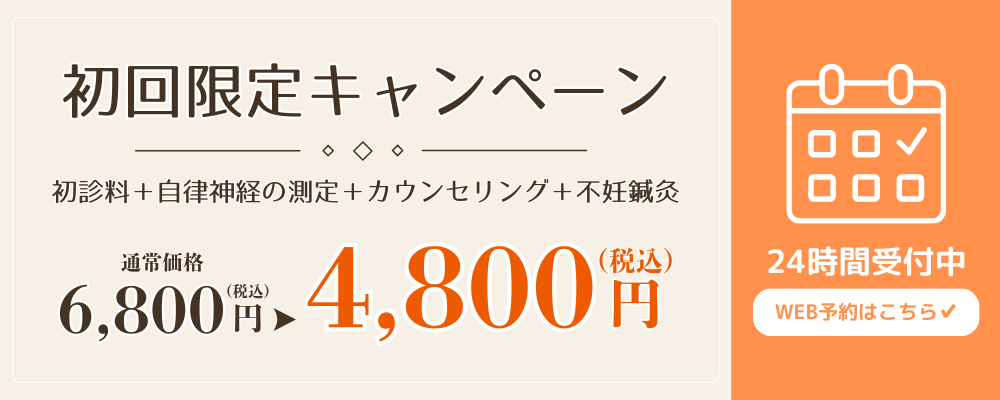2024年12月の投稿記事
冬の妊活を整える養生法とおすすめのツボ
寒さが厳しくなる冬は、動物も植物もひっそりと内にこもる季節です。私たちの身体も、この時期はエネルギーをできるだけ消耗せず、体内に蓄えることが大切です。冬にしっかりと蓄えを行わないと、生命力が芽吹く春を迎える準備が整いません。特に妊娠を目指す方にとって、冬は「腎」を補い、身体を整える絶好のタイミングです。
東洋医学と冬
東洋医学では、冬は「水」と深く関わる季節とされています。身体が冷えやすく、一度冷えると温まりにくくなるのが特徴です。「腎」は冷えに弱く、腎が冷えることでその機能が低下し、生殖機能やエネルギーの巡りにも影響を及ぼします。妊活においても冷えは大敵であり、冬は特に冷え対策を徹底することが重要です。


冬の過ごし方
冬を健康的に過ごし、妊娠力を高めるためのポイントを以下に挙げます。
- 体を芯から温める
お風呂は肩までゆっくりつかり、身体の芯までしっかり温めましょう。髪が冷えると身体も冷えるため、髪を洗った後はすぐに乾かすようにしましょう。 - 適度な運動
ストレッチや体操で体を動かし、エネルギーや血流を巡らせましょう。特に「腎」の経絡が通るふくらはぎの内側のラインを意識したストレッチがおすすめです。足首を直角に曲げ、つま先を外側に開くようにすると、ふくらはぎの内側のラインを効果的に伸ばせます。 - 食事で身体を整える
黒豆、いかすみ、しじみ、えび、味噌など、「黒いもの」や「鹹(しおから)いもの」を取り入れ、腎を補いましょう。これらの食品は血流を促し、冷えた身体を温める効果があります。 - 十分な休息
夜は早めに就寝し、たっぷりと睡眠を取ることでエネルギーを蓄えます。冬は内側にエネルギーを集める季節ですので、無理な活動を避けましょう。
ツボを活用したケア
身体を温め、妊活をサポートするにはツボの活用も効果的です。
- 復溜(ふくりゅう)
足首の内側、くるぶしの少し上に位置するツボで、腎を補い、冷えやむくみを改善します。 - 三陰交(さんいんこう)
足首の内側、くるぶしから指4本分上の場所にあるツボで、血流を促し、ホルモンバランスを整えます。
これらのツボを日々心地よい圧で刺激することで、冷えを和らげ、妊娠に適した環境を整える助けになります。
冬をじっくりと過ごしながら「腎」を補い、春に向けた健康的な身体をつくることで、妊娠力を高める一歩を踏み出しましょう。
参考文献
- 伊藤和憲(2021)『今日から始める養生学』インターナショナル親書
関連記事
妊活中におすすめの適度な運動とは?
妊活中には、適度な運動が心と身体の健康を保ち、妊娠しやすい環境を作るためにとても重要です。しかし、「どの程度の運動が適切なのか?」と迷われる方も多いでしょう。妊活中におすすめの運動とその効果。
妊活中に運動が必要な理由
妊活中に運動を取り入れることには、以下のようなメリットがあります。
- 血流を改善する
運動は血流を良くし、子宮や卵巣に必要な酸素や栄養を届ける助けになります。これは、着床や妊娠の維持にとって重要です。 - ホルモンバランスを整える
適度な運動は内分泌系に良い影響を与え、ホルモンのバランスを保つサポートをします。 - ストレスを軽減する
運動にはリラックス効果があり、ストレスを軽減するのに役立ちます。特に妊活中のストレスは妊娠率に影響を与える可能性があるため、運動で適度に発散することが推奨されます。
どのくらい運動すればいいの?
妊活中におすすめされる運動の頻度や強度は以下の通りです。
- 頻度:週3~5回
- 時間:1回30分~60分
- 強度:「軽く汗をかく」「おしゃべりできるくらいのペース」が目安
無理をせず、身体が気持ちよく動ける程度で始めてみましょう。


妊活中におすすめの運動
- ウォーキング
手軽に始められ、続けやすい運動です。外の空気を吸いながら歩くことでリフレッシュ効果も得られます。 - ヨガ
骨盤周りの柔軟性を高めると同時に、リラックス効果があります。特に妊活ヨガはホルモンバランスを整えるのに効果的です。 - ストレッチ
血流を促進し、身体を柔軟に保ちます。運動前後に取り入れることで、怪我の予防にもなります。 - スイミング(注意あり)
全身運動として非常に優れていますが、水温が低いプールは身体を冷やす可能性があります。温水プールや短時間の利用を心がけましょう。
注意点:やりすぎは禁物!
妊活中の運動は適度が鍵です。以下の点に注意してください。
- 過度な運動を避ける
激しい運動や疲労がたまるほどのトレーニングは、ホルモンバランスを乱し、妊娠に悪影響を及ぼす可能性があります。マラソンやハードな筋トレは避けましょう。 - 冷えに注意する
スイミングのように冷える可能性がある運動では、温水プールを選ぶか短時間で済ませる工夫をしてください。 - 体調を優先する
生理周期や体調に合わせ、無理のない範囲で運動を行いましょう。体調が優れないときは休むことも大切です。
運動と抗酸化の関係
適度な運動には、体内の抗酸化酵素を活性化する効果があるとされています。例えば、スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)やカタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼなどが活性化し、酸化ストレスを軽減します。ただし、過剰な運動は逆に活性酸素を増やし、酸化ストレスを引き起こす可能性があるため注意が必要です。
抗酸化対策としては、運動と併せて以下の栄養素を含む食品を摂取するのがおすすめです。
- ビタミンCやビタミンE
- カロチン類(β-カロチン、リコピンなど)
- ポリフェノール
- コエンザイムQ10
まとめ
妊活中の運動は、健康を保ちつつ妊娠しやすい身体を作るために欠かせません。しかし、やりすぎは逆効果になることもあるため、「適度」を心がけましょう。また、運動の効果を最大限に引き出すために、バランスの良い食事やストレス管理も意識すると良いでしょう。
妊活中の運動に関して不安がある場合は、医師や専門家に相談し、自分に合ったプランを見つけてください。
参考文献
関連記事
年末年始の営業日のお知らせ
【年末年始の営業日のお知らせ】
平素より当鍼灸院をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
年末年始の営業日につきまして、以下の通りご案内申し上げます。
年末最終営業日
2024年12月30日(月)18時まで
休業期間
2024年12月31日(火)~2025年1月3日(金)
年始営業開始日
2025年1月4日(土)通常営業
なお、休業期間中は LINEまたはメール にてお問い合わせを受け付けておりますが、返信が遅れる場合がございます。ご了承ください。


【年末のご挨拶】
本年も多くの皆さまにご来院いただき、心より感謝申し上げます。
2024年はたくさんのご縁に恵まれ、皆さまの健康と妊活をサポートできたことを嬉しく思います。
2025年も引き続き、皆さまの笑顔と健康のお手伝いができるよう、スタッフ一同尽力してまいります。
寒い季節が続きますので、どうぞご自愛くださいませ。
皆さまの年末年始が穏やかで素敵な時間となりますよう、お祈り申し上げます。
それでは、良いお年をお迎えください!
宇都宮鍼灸良導絡院
宇都宮泰子
41歳(子宮筋腫の手術歴・着床不全)胚盤胞3BC、7回目の自費の移植で妊娠
大阪からお越しのKさん(41歳)が体外受精で妊娠されました。
3BCの胚盤胞で妊娠されたKさん
子宮筋腫の手術歴をお持ちのKさんが当院にお越しになったのは2022年5月、すでに2〜3年の不妊期間を経ていました。当時41歳で、ご主人(44歳)とともに大阪の総合病院で顕微授精(保険適用)の段階に進んでいました。
初診時の主な状況
- 年齢・不妊期間:41歳、不妊期間2〜3年
- 既往歴:子宮筋腫(3cm〜10cmの大きさが複数あり、2022年12月に手術済み)
- 月経周期:26〜28日(規則的)、期間7日、経血は暗赤色
- 不定愁訴:肩こり、腰痛、冷え性、頭痛、気圧や天候による体調不良
- 生活習慣:睡眠7〜8時間、自炊中心、週3日缶ビール1本、温活・ウォーキング・白湯を実践
- 服用サプリ:VB、VC、葉酸、亜鉛
- 体外受精の状況:ショート法で採卵済み。初期胚1個、胚盤胞5個を凍結。妊娠(着床)経験なし。
Kさんは、移植に向けた体質改善を目的に当院での鍼灸治療を希望されました。
当院では、Kさんの体質改善を第一に考え、移植周期には子宮へ、採卵周期には卵巣へのアプローチを行う鍼灸治療を週に1回継続しました。
2022年5月:初めての着床と化学流産
鍼灸を開始したこの周期に、初めての凍結融解胚盤胞移植(保険適用1回目)を実施。結果は陽性反応でしたが、hCG値が2桁台と低い反応でした。残念ながら妊娠の維持はできませんでしたが、Kさんにとって初めての着床であり、鍼灸の効果を感じられたそうです。
2023年5月:続く3回の移植で全て陰性
その後、新型コロナウイルス感染症の影響で鍼灸治療を一時お休みされました。その間に、Kさんは同じ総合病院で3回の胚移植(保険適用2~4回目)を行いましたが、結果はすべて陰性でした。
担当医師からは「とにかく移植を続けましょう」という見解でしたが、Kさんは「3回も陰性なのに、ERA検査などの新しい提案もなく、このままで良いのか?」という大きな不安を抱えていました。この悩みを当院にご相談くださり、不妊治療専門クリニックへの転院を検討されることになりました。
2023年7月:転院とPGT-Aによる大きな好転
同総合病院での最後の胚盤胞移植(保険適用5回目)も、hCG値54と低反応でした。
そして、Kさんは新たな可能性を求めて不妊治療専門クリニックへ転院されました。転院後の採卵では、驚くことに胚盤胞7個を凍結することができ、すべてPGT-A(着床前胚染色体異数性検査)に出されました。その結果、正常胚6個、モザイク胚1個という、非常に質の良い結果を得ることができました。
2024年4月:PGT-A正常胚の移植も陰性に
初めてのPGT-Aクリア胚での凍結融解胚移植(保険適用6回目)が行われましたが、判定のhCG値は28.8と低く、残念ながら陰性でした。
2024年9月:7回目の移植でついに妊娠
そして迎えた2024年9月。2回目クリア胚での凍結融解胚移植を実施。Kさんは「これで最後と思い、期待していなかったら妊娠した」と仰っていました。結果は、hCG値1600という数値で陽性反応が出ました。
7回目の移植(保険適用外の自費診療)でのご懐妊でした。現在もマタニティ鍼灸を受けられ、妊娠15週を迎えるKさん。間もなく安定期に入ろうとしています。
Kさん、本当におめでとうございます。出産に向けて、今後もしっかりサポートさせていただきます。ご家族皆さまの幸せを心よりお祈り申し上げます。
妊活成功のための4つのメッセージ
Kさんの妊娠は、長年の努力と適切な選択、そして鍼灸による体質改善が実を結んだ結果と言えるでしょう。彼女の体験から、特に年齢を重ねて妊活に取り組んでいる方に向けて、伝えたい大切なメッセージがあります。
1. 諦めずに続けたからこそ見えた「初めての着床」
鍼灸治療を始めた最初の周期で、Kさんは初めて「着床」という結果を得ました。これは「身体が変われば、結果も変わる」ということを教えてくれる出来事でした。たとえhCGの数値が低くても、“着床できた”という事実は、次の一歩へつながる大切な希望に繋がります。
2. 「クリニック選び」は、治療方針が最重要
Kさんが最初に通っていたクリニックの方針に違和感を抱き、思い切って転院したことで、PGT-Aという新たな選択肢が加わり、状況が大きく好転しました。「自分の身体に合った治療を提案してくれるか」は、通いやすさ以上に、クリニック選びの大きなポイントになります。
3. 鍼灸で「妊娠できる身体づくり」
子宮筋腫という大きな課題を抱えていたKさんは、鍼灸を継続することで体質改善に取り組みました。鍼灸には、以下のような妊活サポート効果が期待できます。
- 卵子の質の向上:卵巣の血流を促し、卵胞の育ちをサポート。
- 子宮内膜を整える:移植周期に重要な子宮環境の血流と厚さを整え、着床率アップに貢献。
- 身体の土台づくり:不調の改善やストレス軽減により、妊娠しやすい心と体のバランスを整える。
4. 妊娠は、思いがけない時にやってくる
Kさんは「これで最後、もう期待しない」と思っていたタイミングで妊娠されました。プレッシャーから少し解放されたことで、心も体もリラックスし、本来の妊娠力が発揮されたのかもしれません。
妊活では、「続けるか・やめるか」「今の治療を信じていいのか」と迷うことも多いかもしれません。でも、自分の身体の声を大切にしながら、信頼できる医療やサポートと出会えれば、前に進む力がきっと湧いてきます。
不妊治療の効果を最大限引き出すために、鍼灸で「妊娠・出産ができる身体づくり」を事前に、できるだけ早い段階から始めることが大切です。もし、なかなか思うような結果にならないと感じているなら、それはまだ「妊娠・出産ができる身体づくり」が十分にできていないのかもしれません。週に1回の鍼灸を取り入れてみませんか?
年齢や治療歴を問わず、あなたの「妊娠したい」という想いを、私たちは全力でサポートいたします。
不妊治療において、胚盤胞のグレードは気になるところです。「3BC」という評価を受けた場合、一般的に「良好胚」とは言いにくい側面はありますが、妊娠の可能性がゼロというわけでは決してありません。
ここでは、文献やクリニックの臨床報告に基づき、「3BC 胚盤胞の妊娠率の目安」と、確率に影響する因子について解説します。
胚盤胞のグレード「3BC」とは?
胚盤胞の評価(Gardner分類など)は、「数字+内細胞塊(将来の胎児)+栄養外胚葉(将来の胎盤)」という3つの要素で決まります。3BCの場合は以下の通りです。
- 数字(3)→ 胚の膨張度・発育段階
「3」は、腔(ブラストシール)が十分に拡大している状態。 - 内細胞塊(B)→ 将来、胎児になる部分
B:細胞数が多いが、やや粗造な部分がある。 - 栄養外胚葉(C)→ 将来、胎盤になる部分
C:細胞が少なく、形態がやや劣る。
このように、「3BC」は胎盤になる部分の評価が「C」であり、形態がやや劣ると見なされることがあります。
「3BC 胚盤胞」の妊娠率の目安
「C」を含む胚盤胞の妊娠率は、一般的に「A」や「B」主体の良好胚よりも下がる傾向があります。しかし、具体的な妊娠率(胎嚢確認)については、国内のクリニックの報告などでは、以下のようなデータが示されています。
- 20〜25%程度(胎嚢確認)【越田クリニック(5日目 3BC)】
- 43.9%(臨床妊娠率)※グレード「BC」全体での報告【他の臨床報告例(BC全体)】
これらの報告を総合すると、5日目発育の「3BC」胚盤胞の妊娠率(胎嚢確認レベル)は、20〜30%前後が現実的な目安と考えられます。
注意点:これは「妊娠(胎嚢確認)」の確率であり、最終的な「出産率」はこれよりも低くなる可能性があります。また、報告されている確率は、クリニックの技術レベルや対象とする患者さんの年齢層によって変動します
妊娠の可能性を大きく左右する要因
胚盤胞のグレードは重要な要素ですが、妊娠の成功は他の多くの要因によって決まります。特に以下の要素が、妊娠率に大きく影響します。
① 患者さんの年齢
最も大きな要因の一つです。年齢が上がるほど、胚の染色体異常率が高くなるため、グレードに関わらず着床率や妊娠継続率が低下する傾向があります。
② 胚の発育日数
5日目で胚盤胞になったか vs 6日目で胚盤胞になったかでは、妊娠率が異なる場合があります(特に形態良好胚では5日目の方が高い傾向)。また、「3BC」が5日目か6日目かによっても、確率は変動する可能性があります。
③ 子宮・内膜環境
胚を受け入れる子宮内膜の厚さ、血流、炎症状態などが着床に大きく影響します。どんなに良い胚でも、子宮側の環境が整っていなければ着床は難しくなります。
④ 移植方法・補助技術
アシストハッチング(AHA)の実施、適切なホルモン補充、移植時期の調整なども、成功率に影響を与える可能性があります。
「3BC」の胚盤胞は、形態面で懸念があるものの、妊娠の可能性は十分にあります。確率の目安は20〜30%前後ですが、あなたの年齢や子宮環境などによって、この数値は大きく上下します。
グレードはあくまで参考情報の一つです。最終的な見通しや治療計画については、あなたの状態を最もよく把握している主治医とよく相談することが大切です。
Kさん妊娠お喜びの声
▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください。
タイミング・人工授精4回しましたがかすりもせず、体外受精にステップアップしました。着床UPに鍼灸が良いと聞いたので、体質改善の為にも試してみようと思いました。
▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください。
体外受精(顕微授精/胚盤胞移植(凍結胚)/着床前胚異数性検査(PGT-A))
▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください。
ストレッチ・サプリメント・自宅灸・レーザー・温活・ウォーキング
(ビタミンD不足だったので基準値に達するように飲み続けました。ウォーキングや自宅灸をする事で普段から体が暖まって良かったと思います。)
▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください。
治療の段階に合わせた施術をして頂けます。他院ではここまで特化した専門的な施術は受けられなかったので、安心しておまかせできる信頼感があります。不妊治療はなかなかまわりに相談できない事が多く孤独になりやすいですが、こちらの先生方に悩みや心配事などいつも相談に乗っていただしていたので唯一の心の拠り所でもあります。肩こりや腰痛などその日の不調も治して頂けるので帰りは体が軽くぽかぽかして帰れます。
▢ 同じように悩まれている方へアドバイス(ご自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など) やメッセージがあればお願いいたします。
保険適用の6回で出来なければ、辞めようと思っていましたが6回目の移植も化学流産(3回目)で継続できず、もう無理かと落ち込みました。PGT-Aに出した正常胚がまだ3つ残っていた為、消化試合のつもりで臨んだ自費での移植で妊娠し、現在15週めです。 グレードも「3BC」で良い方ではなかったのでびっくりしました。移植の前に一度休んで頑張るのをやめて旅行へ行ったりリフレッシュできたのも良かったのかもしれません。あと多少高くても専門の病院へ行くべきだと思いました。5回の移植は総合病院だったので、、、。もっと早く転院すれば良かったなと今では思います。
※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。
🤰こちらの妊活ブログもおすすめです
卵子の質を高める6つの生活習慣とは?
「卵子の質を高めたいけれど、何をすればいいのかわからない…」そんな悩みを抱えていませんか?今回は、卵子の質をサポートするために今日からできる具体的な6つの方法をご紹介します。無理なく、楽しく取り組んでみましょう!
方法① 栄養バランスを整えた食事を心がける
私たちの体は食べたもので作られています。特に抗酸化作用のある食品は、卵子を酸化ストレスから守る助けになります。
- おすすめの食品:
ブルーベリー、アーモンド、緑黄色野菜、魚など - 控えるべき食品:
白砂糖や精製された炭水化物は血糖値を乱しがちなので、控えめに。
ポイントは「彩り豊かなプレート」を意識すること。食事が楽しくなるだけでなく、必要な栄養素をしっかり摂ることができます。
方法② 適度な運動を取り入れる
激しい運動は必要ありませんが、軽めの運動を習慣化することが大切です。ウォーキングやヨガは血流を促進し、卵巣への栄養供給を助けてくれます。
運動のポイント
- 1日20~30分のウォーキング
- ヨガやストレッチでリラックス
これなら忙しい日々の中でも取り入れやすいですよね。
方法③ 良質な睡眠を確保する
睡眠中に分泌される成長ホルモンは、細胞の修復や再生を促進します。不規則な睡眠はホルモンバランスを乱す原因に。
良質な睡眠を得るために
- 寝る1時間前にスマホやパソコンをオフに
- 毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きる
7~8時間の睡眠を目標にしましょう。
方法④ ストレスをためない
ストレスはホルモンバランスに悪影響を及ぼします。日常生活の中でリラックスできる時間を大切にしましょう。
ストレス解消のヒント
- 深呼吸や瞑想
- お気に入りの音楽を聴く時間を作る
- 趣味に没頭する時間を持つ
方法⑤ 冷えを改善する
冷えは血流を妨げ、卵巣の働きにも影響します。「冷やさない」を意識した生活を心がけましょう。
冷え対策のアイデア


- 足湯や湯たんぽの活用
- 温かいハーブティーを飲む
- 腹巻やレッグウォーマーを着用する
身体を温めることで、全身の巡りも良くなります。
方法⑥ サプリメントや鍼灸を活用する
必要に応じて、卵子の質をサポートするサプリメントを取り入れるのも良い方法です。また、鍼灸や漢方は東洋医学の視点から血流やホルモンバランスを整えるのに役立ちます。
おすすめの栄養素
- コエンザイムQ10: 抗酸化作用で卵子を守る
- ビタミンE: 血流改善と細胞保護
- 亜鉛: ホルモンバランスのサポート
まとめ
卵子の質を高める方法は、どれも日常生活の中で少し意識するだけで取り入れられるものばかりです。一つずつ無理なく試してみてくださいね。未来の自分に感謝されるような生活習慣を一緒に目指しましょう!
参考文献
- Broekmans, F. J., Soules, M. R., & Fauser, B. C. (2009).
- Ovarian aging: mechanisms and clinical consequences.
Endocrine Reviews, 30(5), 465-493.
関連記事
ストレートネックは自律神経を乱す?首こり・不調の原因と東洋医学的対処法
ストレートネックがもたらす自律神経の乱れと首ケアの重要性
現代社会で多くの人が悩む「ストレートネック」や「スマホ首」は、単なる首の問題にとどまらず、全身の健康に影響を及ぼす可能性があります。松井先生の研究によれば、首の筋肉(頸筋)の異常が原因となり、自律神経失調やさまざまな不定愁訴を引き起こすことがあるのです。この状態を「頸性神経筋症候群」と呼び、首の健康が全身の健康に直結することが分かっています。
頸性神経筋症候群が引き起こす主な症状
以下のような症状が、頸筋の治療を通じて改善されることが確認されています。
- 筋緊張性頭痛や一部の片頭痛
- めまい
- 自律神経失調症
- パニック障害
- 新型うつ(頸筋性うつ)
- 頸椎捻挫
- 更年期障害(難治性や若年性も含む)
- 慢性疲労症候群
- ドライアイ
- 多汗症
- 機能性胃腸症
- 過敏性腸症候群
- 機能性食道嚥下障害
- 血圧不安定症
- VDT症候群(長時間のディスプレイ作業による不調)
これらの症状は、従来の医療では「不定愁訴」とされ、十分な治療が行われていないケースが多いとされています。
頸性神経筋症候群の主な原因
頸性神経筋症候群の原因には以下の要因があります。
ムチウチや頭部外傷
事故やケガによる首へのダメージ。パソコンやスマートフォン、ゲームによる首の過労
長時間のデスクワークやスマホ使用が頸筋に過剰な負担をかけます。同じ姿勢を続ける作業
長時間の流れ作業や不良姿勢が筋肉の疲労を促進します。筋肉疲労と乳酸の蓄積
首の筋肉が硬直すると、酸素不足で乳酸が溜まり、硬化や痛みを引き起こします。
筋肉が過労状態に陥ると、酸素不足でエネルギー代謝が不完全となり乳酸が溜まります。この乳酸が蓄積し続けると、筋肉が硬化し、健康に大きな影響を及ぼします。


首を冷やさないことの重要性
松井先生は、首を冷やすことが体に与える悪影響についても警鐘を鳴らしています。
首の冷えがもたらす問題
首が冷えると血管が収縮し、筋肉が硬くなり、酸素と栄養が行き渡らなくなります。その結果、老廃物が溜まり、不定愁訴が現れやすくなります。冷え対策
夏でも冷房で首が冷えやすい環境が増えています。首を冷やさないために、スカーフやタオルを活用し、汗を拭いた後で首を覆うなどの対策が有効です。また、お風呂上がりに濡れた髪を放置せず、ドライヤーでしっかり乾かすことが大切です。
頸筋の治療法
文献では、以下のような治療法を提唱しています。
- 低周波療法
筋肉の硬直をほぐすために用いられます。 - 温熱療法
筋肉の柔軟性を改善し、血流を促進します。 - 薬物療法
必要に応じて補助的に使用されることがあります。
また、日常生活でのセルフケアも推奨されます。特に入浴は首を温める最適な方法であり、全身浴を通じて筋肉の緊張をほぐし、副交感神経を活性化する効果があります。
首の健康が全身の健康に繋がる
「首を守ること」は、単なる痛みやコリの解消だけではなく、全身の不調を改善し、日々の生活を快適にするカギとなります。ストレートネックやスマホ首を放置せず、適切なケアを心がけましょう。首をいたわることで、心も体も健康的な毎日を手に入れることができるはずです。
参考文献
- 松井孝嘉(2012)「頸性神経筋症候群」『NURES TREND』7月号
- 松井孝嘉『「スマホ首」が自律神経を壊す』
関連記事
【首の冷えが原因?】寝ても取れない疲れと睡眠の質の関係性|自律神経を整える就寝時の首ケア
「ぐっすり眠ったはずなのに、なぜか朝から体が重い…」「寝ている間に首が冷えて、疲れが取れない気がする…」
もしあなたがそう感じているなら、その不調は、眠っている間の「首の冷え」が原因かもしれません。首は、脳と全身をつなぐ非常に重要な部位であり、そのケアがおろそかになると、睡眠の質や日中の体調に大きな影響を及ぼします。
本記事では、首の冷えが睡眠の質を低下させ、慢性的な疲労につながるメカニズムを、特に自律神経との関係に注目して詳しく解説します。
首の冷えが「疲れ」につながるメカニズム
首は、脳への血流や体温調節に大きく関わる部位です。就寝時に首が冷えすぎると、体温調節中枢が誤作動を起こし、深部体温がスムーズに下がりにくくなり、眠りが浅くなる可能性があります。
眠っている時に首を冷やすことが疲労感につながる主な理由は、以下の3つのメカニズムが関係しています。
1. 自律神経機能の乱れ:深い睡眠の妨げ
首には、体の機能を調整する自律神経(交感神経と副交感神経)の通り道があります。
- 冷えによるストレス: 首が冷えると、体はストレスを感じ、リラックス時に優位になるべき副交感神経の働きが抑制され、緊張時に働く交感神経が優位になりやすくなります。
- 睡眠の質の低下: 交感神経が優位な状態では、体を修復する深い睡眠(ノンレム睡眠)が妨げられ、眠りが浅くなる傾向があります。これにより、体が十分に休息できず、夜間覚醒が増えるほか、疲労回復力が低下して翌朝の疲労感につながります。
2. 脳への血液循環の低下:疲労物質の滞留
首には、脳に酸素と栄養を供給する重要な血管(頸動脈や椎骨動脈)が通っています。
- 血管の収縮: 首が冷えるとこれらの血管が収縮し、血流が悪くなります。
- 酸素・栄養不足: 脳や全身の筋肉への酸素供給が不足し、疲労物質の排出も滞るため、首・肩こりや頭痛、そして翌朝に強い疲労感が残ってしまう可能性があります。首は「脳の延長部分」とも捉えられるほど、脳への影響が大きいため、特に注意が必要です。
- 老廃物の排出停滞: 首の周りには、体内の老廃物や不要な水分を排出するリンパ節が集中しています。首が冷えることでリンパ液の流れが悪くなると、老廃物の排出が滞り、首や肩のこり、全身のむくみや疲労感として現れることがあります。
- 免疫力の低下: 首の冷えによる自律神経の乱れや血流悪化は、免疫力の低下も招き、慢性的な疲労感につながると考えられます。
- ネックウォーマーや薄手のスカーフ: 睡眠中に首元が冷えやすいため、締め付けすぎない、ゆったりとした素材のネックウォーマーや薄手のスカーフ、またはタートルネックのパジャマなどを着用し、首を冷気から守りましょう。
- 寝具の調整: 枕や掛け布団で首回りの温度を適切に保ちます。深部体温を下げる(入眠を促す)一方で、首元は冷やしすぎない温めと放熱のバランスが重要です。
- 高さと形状: 首のカーブに合った、適切な高さと形状の枕を選ぶことが非常に重要です。不適切な枕は首に負担をかけ、血管や神経を圧迫し、睡眠の質を悪化させる可能性があります。
- 素材: 柔らかすぎず硬すぎない、適度な反発力のある素材がおすすめです。
- 室温・湿度: 寝室が寒すぎると、無意識に体が緊張し首も冷えやすくなります。就寝中も適度な室温(一般的に18〜22℃程度)に保ち、また、適切な湿度(50〜60%)を保ちましょう。
- 冷房対策: 冷房の風が直接首に当たらないように、風向きを調整するか、寝る位置を工夫しましょう。
- 松井孝嘉(2012)「頸性神経筋症候群」『NURES TREND』7月号
- 松井孝嘉『「スマホ首」が自律神経を壊す』
- Okamoto-Mizuno K, Mizuno K. Effects of thermal environment on sleep and circadian rhythm. Journal of Physiological Anthropology. 2012;31:14.
- Lan L, Qian XL, Lian ZW, Lin YB. Local body cooling to improve sleep quality and thermal comfort in a hot environment. Indoor Air. 2018 Jan;28(1):135-145. doi:10.1111/ina.12428.
- Xu X, et al. A review of human body temperature, sleeping thermal comfort and sleep quality. ScienceDirect Review. 2024.
- Minor K, Bjerre-Nielsen A, Jonasdottir SS, Lehmann S, Obradovich N. Ambient heat and human sleep. arXiv. 2020 Nov 13.
3. リンパの滞りと免疫力の低下
質の良い睡眠と健康のための「首の温熱ケア」
首を冷やさないようにすることは、質の良い睡眠と自律神経のバランス維持に非常に効果的です。今すぐ始められる具体的なケア方法をご紹介します。
1. 就寝時の温熱管理
2. 適切な枕の使用
3. 寝室環境の管理
💡豆知識:冷やしすぎも逆効果
研究では、高温環境下での首や背中の局所的な冷却が睡眠効率を改善することも報告されていますが、日常的な環境で首を冷やしすぎることは、自律神経リズムの乱れや血流悪化、睡眠の質低下を招くリスクが指摘されています。
首を守って、スッキリ目覚める毎日を!
首は、脳への血流、神経伝達、自律神経の調整など、私たちの健康を支える上で欠かせない重要な役割を担っています。眠っている間に首を冷やすことは、これらの機能に悪影響を及ぼし、自律神経の乱れ、血液循環の低下、疲労感の蓄積を招く原因となります。
ぜひ、今夜から寝るときの首のケアを取り入れてみてください。適切な首の温熱ケアで、血流やリンパの流れが整い、自律神経のバランスが保たれやすくなります。翌朝の目覚めがスッキリとし、「だるい」から「スッキリ!」に変わるはずです。
妊活中の方へ
妊活においても、首の冷えは軽視できません。首の血流が悪化し自律神経が乱れると、全身の血行が低下し、子宮・卵巣への栄養や酸素の供給が不足します。これは、卵巣機能の低下や着床率低下、ホルモンバランスの乱れにつながり、妊娠成立に不利な状態を招きます。妊活中は特に首元の冷え対策を行い、睡眠の質を保つことが、妊娠しやすい体作りへ直結します。
Q. 就寝中に首が冷えると、なぜ疲れが取れないのですか?
自律神経が乱れるからです。首の冷えがストレスとなり、リラックスに必要な副交感神経の働きを弱め、深い睡眠(ノンレム睡眠)が妨げられ、疲労回復が不十分になります。
Q. 首の冷えは他にどのような悪影響がありますか?
血流が悪化し、脳への酸素や栄養の供給が不足するため、首・肩こり、頭痛、慢性的な疲労感につながります。また、体温調節が乱れ、入眠しにくくなることもあります。
Q. 首の冷えを防ぐには、どうすれば良いですか?
首元を適切に保温しましょう。締め付けないネックウォーマーや薄手のスカーフを活用し、冷房の風が直接当たらないように注意します。また、首のカーブに合った枕を選ぶことも重要です。
Q. 妊活中に首の冷え対策は必要ですか?
はい、非常に重要です。首の冷えによる血流や自律神経の乱れは、子宮・卵巣への血行を悪化させ、卵巣機能の低下や着床率の低下につながる可能性があるため、対策が推奨されます。


📚参考文献
妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?
首の冷えや自律神経の乱れによる不調、妊活のお悩みはございませんか?
宇都宮鍼灸良導絡院では、お一人おひとりの体質に合わせた施術をご提供しております。ご予約はこちらからお気軽にご相談ください。🍀