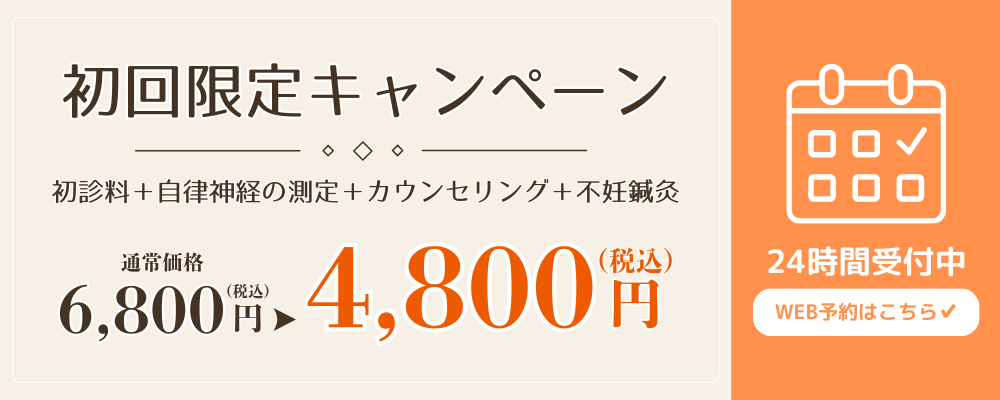2025年04月の投稿記事
妊活・妊娠中のヘアカラー・パーマは大丈夫?【胎児に与える影響とは】
「妊活中に髪を染めてもいいの?」
「胚移植後はヘアカラーを控えた方がいいの?」
「妊娠中にパーマをかけたいけれど、赤ちゃんへの影響は?」
妊活や妊娠中は、普段の美容習慣についても「本当に大丈夫かな?」と不安に感じるもの。特に化学薬品を使うヘアカラーやパーマは、妊娠や胎児への影響が気になるテーマです。ここでは最新の研究やガイドラインを踏まえて、安全性と注意点を詳しく解説します。
現時点での科学的知見
- 確定的なリスクは示されていない
これまでの研究では、妊娠中のヘアカラーやパーマが胎児へ直接的な大きな悪影響を与えるという明確な証拠はありません。 - ただしリスクゼロではない
染毛剤やパーマ液にはアレルギーを起こす成分や、動物実験で生殖細胞毒性が示された物質が含まれることがあります。2001年の調査では酸化染毛剤に「環境ホルモン作用」が確認され、2015年には消費者庁が注意喚起を行いました。 - 国際的なガイドライン
欧州産科婦人科学会(2022年)は「妊娠中のヘアカラーのリスクは非常に低い」としていますが、「低い」=「ゼロ」ではありません。妊活中や胚移植直後といったデリケートな時期は、不要な化学物質への暴露をできるだけ避けるのが望ましいとされています。
妊活中・妊娠中に気をつけたいポイント
- 妊娠初期(12週まで)は避ける
胎児の器官形成が進む時期の施術はできるだけ控えるのが安心です。 - 低刺激・植物由来の製品を選ぶ
ヘナやカラートリートメントなど、化学物質の刺激が少ない製品がおすすめです。 - パッチテストを必ず行う
妊娠中は肌が敏感になりやすく、アレルギーを起こしやすいので事前確認が必須です。 - 換気を徹底・吸入を避ける
揮発性物質を吸い込まないよう、通気の良い環境で施術を。美容室でも換気の確認をしましょう。 - 頭皮への薬剤付着を最小限に
地肌に直接薬剤をつけないように、美容師さんに相談すると安心です。 - 医師や美容師へ相談
不安が強い場合は、必ず担当の産婦人科医や不妊治療専門医に確認しましょう。
美容師さん自身へのリスクも
美容師は日常的にヘアカラー剤やパーマ液を扱うため、一般の人に比べて化学物質への暴露量が多くなります。そのため、以下のようなリスクが報告されています。
- 生殖への影響:美容師は不妊や月経不順のリスクがやや高まる可能性があるとされています。
- 妊娠経過への影響:流産、早産、低出生体重児のリスクが増える可能性が指摘されています。
- 胎児への影響:一部の研究では、先天性異常や周産期死亡の発生率上昇の可能性が報告されています。ただし因果関係はまだ確立されていません。
美容師が取るべき対策
- 換気設備を整える
- ゴム手袋やマスクを使用する
- 化学薬品の使用マニュアルを守る
自宅カラーと美容院カラーの違い
自宅でのヘアカラー
- メリット
・使用頻度を自分で調整できる
・施術時間を短く済ませやすい - リスク
・薬剤が頭皮に直接触れやすい
・換気不足の環境で使用すると、揮発物を吸い込みやすい
・使用方法の誤りによる皮膚炎リスク
美容院でのヘアカラー
- メリット
プロが頭皮に薬剤をつけないよう工夫してくれる
換気設備が整っているサロンが多い
髪質や体調に合わせて低刺激の薬剤を選んでもらえる - リスク
・美容師が日常的に多くの薬剤を扱うため、施術側にとっては蓄積リスクがある
・サロン内の薬剤濃度が家庭より高くなる場合がある
・妊婦が長時間滞在することで吸入リスクが増える
どちらが安全?
妊娠中の女性にとっては 美容院でプロにお願いする方が比較的安心。ただし、美容師自身は日常的に化学物質へ暴露されるため、職業上の対策が必須です。自宅カラーを選ぶ場合は、換気を徹底し、薬剤が頭皮に触れないように注意しましょう。
まとめ
妊活中や妊娠中のヘアカラーやパーマは「絶対にNG」ではありませんが、「安全が完全に保証されているわけでもない」というのが最新の知見です。
特に妊娠初期や胚移植後は控えめにし、安定期以降は低刺激製品の選択・パッチテスト・換気・頭皮保護を徹底することでリスクを下げることができます。


📚参考文献
- Chua-Gocheco A, Bozzo P, Einarson A. A study on the safety of hair dyes and perms during pregnancy. J Occup Med Toxicol. 2010;5:24.
- European Society of Gynaecology. 欧州産科婦人科学会ガイドライン(2022年発表):妊娠中の美容に関する推奨事項.
- 消費者庁 消費者安全調査委員会. 毛染めによる皮膚障害に関する注意喚起. 2015年10月23日.
- NPO法人 食品と暮らしの安全(旧 日本子孫基金). ヘアカラー剤の成分と環境ホルモン作用に関する報告. 2001年.
GWの営業について
【ゴールデンウィーク期間中の営業について】
いつも当院をご利用いただき、誠にありがとうございます。
ゴールデンウィーク期間中も、通常通り営業しております(木曜日は定休日となります)。
なお、祝日は土日と同じ営業時間となりますので、ご注意ください。
ご予約が混み合う時期となりますので、お早めのご予約をおすすめいたします。
皆さまのご来院を心よりお待ちしております。
33歳 1人目に続いて2人目妊活も鍼灸とタイミング法で妊娠
大阪市からお越しのMさん(33歳)が妊娠されました。
患者情報
- 来院の動機:体質の改善、不妊症
- 鍼灸の経験:あり(1人目妊活の時、当院で鍼灸を受けて妊娠・出産。今回も2人目妊活で来院。)
- 体調:良好
- 体質:肩こり、冷え性、むくみ
- 睡眠:23時~6時(平均7時間)
- 生理:順調で25~30日で規則的、生理痛・PMSはなし。経血の色は赤色。
- 食生活:1日3食、食の趣向は甘いものを好む。飲み物はお茶、ジュース(1日3杯ほど)、お酒とたばこはなし。
- 運動:あまりしない(子育てで時間が確保しにくい)
- 入浴:全身浴
- 現在服用している薬・サプリメント:エタネルセプト(1人目産後から関節リウマチを発症)、葉酸(ドリンクタイプ)。
- ご主人は31歳。男性不妊の原因は不明。(検査を受けたことがない)
- ご自身で行っているセルフ妊活は、自宅でお灸をする。(火を使わないタイプ)
当院にお越しになるまでの経緯
Mさんは、以前1人目妊活の際にも当院で鍼灸を受けられてれ、自然妊娠されました。出産から1年が経過し、今回も2人目妊活のために再びお越しになりました。
現在はクリニックへの通院はされておらず、自己流タイミングを続けているとのことでした。過去の検査では左側卵巣嚢腫(3.5cm)があり、経過観察中です。鍼灸による体質改善と自然妊娠をご希望でした。
不妊鍼灸を始めてから、妊娠に至るまで
鍼灸は、肩こり・腰痛・便秘などその日の体調に応じた施術に加え、タイミングで妊活されているので卵巣の血流を促進し、質の良い卵子が育つように目指す施術を毎回行いました。
当院は、卵巣や子宮の生殖機能の向上だけでなく、体のさまざまな不定愁訴(心身の不調)にも徹底して施術をしています。心と身体が健康な状態は妊娠しやすいシステムがはたらきやすくなります。しかし、実際には、妊活中の方の多くが、心と体の不調を抱えていることがあります。これは、妊娠しやすいシステムがうまくはたらいていないということが考えられます。
なぜなら、人間の体は「ホメオスタシス(生体恒常性維持)」によって健康を保っています。これは、自律神経(交感神経と副交感神経)、内分泌系(女性ホルモンなど)、免疫系(細菌・ウィルスから体を守る)などがバランスよくはたらいている状態が健康と呼ばれます。このホメオスタシスは、さらに多様な器官や内臓など全身に複雑に関連して生命を維持しています。
人間は体のどこかの機能が低下しホメオスタシスが乱れると、その機能低下を回復させ、健康な状態に戻そうとするため、その代償として最初に「生殖能力活動」を低下させる若しくは止めてしまい、妊娠しづらい状態になると考えられています。
そのため当院では、卵巣・子宮の血流促進を図り、卵胞の発育促進や薄かった内膜が厚く成長できるよう目指して鍼灸施術を行っています。また、スーパーライザー(直線偏光近赤外線)を使用し、過緊張をおこしている交感神経を正常な状態に調整し、卵巣の血流をより良い状態に目指します。
不妊鍼灸では、卵巣・子宮や自律神経が注目されがちですが、実際には全身の器官が複雑に連携しているため、体全体の健康状態も同時に整えるようアプローチしています。そのため、首肩こり、頭痛、腰痛、便秘、冷え性など体の不調にも対応し、心と体が楽になっていただけるように施術を行っています。
Mさんの場合も、日頃から首や肩腰の痛み、便秘、むくみなどがあり、「仕事と育児で大変」と仰っていました。毎回、問診で伺った不調に合わせた施術を行い、体が楽になるように努めました。鍼灸を続ける中で、月経周期が28~30周期と安定するようにもなりました。お仕事はデスクワークと立ち仕事の両方があり、加えて育児もあるため、1人目妊活と比べて、タイミングが思うようにとれないことがお悩みでした。
鍼灸を始めて半年ほど経過した頃、ご本人は人工授精をお考えでしたが、ご主人は望んでおらず、精液検査も受けたことがないとのことでした。そのため、施術中にはご主人が検査に行ってくれるように、必要性をお話させていただき、Mさんもご主人に何度も訴えかけられました。
その結果、2024年8月にご主人が初めてクリニックの検査(血液検査)を受けられました。結果は問題なく、「今後は人工授精も良いかも。」と前向きな姿勢になっていただけました。そして、その次の周期でなんと自然妊娠していることが分かりました。胎嚢・心拍も確認できました。
その後、マタニティ鍼灸を32週まで受けられ、妊娠維持を目的とした施術に加え、つわりや腰痛、便秘などにも対応しました。28週の時には逆子だったため、3回の逆子鍼灸とご自宅のお灸と逆子体操で無事元通りになりました。妊娠32週で当院の鍼灸は卒業されました。
ご主人がクリニックの検査を受けられたことや人工授精を前向きになったことが、Mさんの精神面への安心につながり、妊娠するきっかけになったのかもしれません。また、約1年間鍼灸を続けたことで妊娠・出産できる良質な卵子が育ってくれたのかもしれません。
Mさん、この度は本当におめでとうございます。もうすぐ出産ですね。無事出産されることを願っております。「目標は3人」と仰っておられましたので、3人目妊活の時もサポートさせていただきますのでまたよろしくお願いいたします。
Mさん妊娠お喜びの声
▢ お悩みの症状またはご来院当初の目的をお聞かせください
半年ほど自己流でしていましたが、体を整えようと思って通いはじめました。また、1人目も通いはじめてすぐ妊娠したので、効果があると思っていました。
▢ 鍼灸以外で妊娠(陽性反応)された方法に〇をつけてください
タイミング(病院で排卵日を見てもらって、タイミングを取っていました。)
▢ ご自身で「これは良かった!」「自分に合っていた!」と思われた妊活があればお教えください
自宅灸・レーザー・温活
▢ 鍼灸施術を受けていただいた感想をお聞かせください
鍼灸施術を受けて、生理周期が整ったのがいちばん良かったと思います。また、足の冷えや腰の張りも見てもらえて、体が楽になりました。他にも体に良いものや、気をつけた方がいいコト等、アドバイスをいただけるのもとても助かりました。
▢ 同じように悩まれている方へアドバイスに自身でやって良かったこと、若しくは続けることが出来たセルフ妊活など)やメッセージがあればお願いいたします。
自分で火のいらないお灸をしていたのですが、リラックスできてよかったと思います。ツボは教えてもらって、そこに家でお灸をしていました。2人目妊活は、子どもがいる分、1人目とは生活が変わってしまっていて、思うようにいかないコトが多かったですが、リラックスできる時間を取るコトは大切だと思いました。
※【免責事項】すべての方にあてはまるものではありません。効果の実感には個人差があります。
関連記事
フェロモンとホルモンの違いとは?妊活にも関わる”におい”の科学
「フェロモンが多い人は、女性ホルモンも多いの?」
妊活中の方や体質改善に取り組む方から、このようなご質問をよくいただきます。一見似ているようで、実は全く異なる役割を持つ「フェロモン」と「ホルモン」。その違いを理解することは、妊活だけでなく、日々の健康管理にも役立ちます。
この記事では、フェロモンとホルモンの科学的な違い、その関係性、そして東洋医学の視点も交えながら、魅力を引き出す身体づくりについて詳しく解説します。
ホルモンとは?体内で働く情報伝達物質
ホルモンは、体内の特定の臓器(内分泌腺)でつくられ、血液に乗って全身を巡り、特定の細胞や器官に作用して、身体のさまざまな生理機能を調節する化学伝達物質です。いわば、身体の各部署に指示を出す「指令役」のような存在です。
- 女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン): 月経周期、排卵、妊娠、出産、骨の健康、皮膚の状態などに深く関わります。妊活においては、そのバランスが極めて重要です。
- 甲状腺ホルモン: 代謝や成長、エネルギー消費を調節します。
- ストレスホルモン(コルチゾールなど): ストレス反応に関与し、血糖値や免疫機能を調節します。
ホルモンは、身体の内部で完結する情報伝達システムであり、意識することなく、私たちの生命活動を維持するために不可欠な役割を担っています。
フェロモンとは?体外で情報を伝える化学物質
一方、フェロモンは、身体の外に分泌され、同じ種の他の個体に特定の情報(行動や生理反応)を伝える化学物質です。主に汗、皮脂、尿などから分泌され、空気中を介して相手に届きます。
動物の世界では、フェロモンは繁殖行動の誘発、なわばりの主張、危険信号の伝達など、生存や種の保存に不可欠な役割を担っています。例えば、昆虫が性フェロモンで異性を誘引する現象はよく知られています。
ヒトにおけるフェロモンの存在とメカニズム
ヒトにおいても、フェロモン様の化学物質が、意識することなく感情や行動に影響を与える可能性が指摘されています。特に、「ヒトフェロモン」として研究されているのが、体臭に含まれるステロイド系の物質や、腋窩(脇の下)から分泌される特定の揮発性物質などです。
ただし、動物のように明確な繁殖行動を誘発する「性フェロモン」がヒトに存在するかどうかについては、まだ未解明な部分が多く、現在も活発な研究が続けられている分野です。しかし、特定の体臭が他者に無意識のうちに魅力や不快感を与えることは経験的に知られています。
フェロモンと女性ホルモンの関係性:直接的ではないが関連性あり
「フェロモンが多い人は、女性ホルモンも多いのですか?」という問いに対し、フェロモンと女性ホルモンは直接的な相関関係にあるわけではありません。 フェロモンは体外に分泌される化学物質であり、ホルモンは体内を巡る情報伝達物質だからです。
しかし、両者には間接的な関連性があると指摘されています。
例えば、女性ホルモンのひとつであるエストロゲン(卵胞ホルモン)の分泌が活発になる排卵期には、皮膚の状態や体臭に変化が現れ、フェロモンがより強く感じられるという研究報告があります。
ある研究では、排卵期の女性の体臭に男性がより魅力を感じるという結果が報告されており、これはホルモンの変化がフェロモンの表れ方に影響する可能性を示唆しています。つまり、ホルモンバランスが整っていることは、フェロモンが魅力的にあらわれやすい身体環境をつくると言えるでしょう。
フェロモンの「多い・少ない」とピークは?
フェロモンは、誰にでも分泌されているものですが、その量や「にじみ出かた」には個人差があると考えられています。
フェロモンの質に影響を与える要因
- ストレス: 交感神経が過剰に働き、心身のバランスが崩れると、皮膚のコンディションや分泌物にも影響が出ることがあります。
- 生活習慣の乱れ: 寝不足、過労、偏った食生活なども、身体のバランスを崩し、フェロモンの質に影響を与え得ます。
これらは、東洋医学でいうところの「気血津液(きけつしんえき)の乱れ」にも対応します。身体全体のバランスが崩れることで、汗や皮脂といった「外に出るサイン」にも変化が現れ、結果的にフェロモンが持つ魅力が弱まると考えられます。
フェロモンのピーク
一般的には、ホルモンバランスや皮脂腺の働きが最も活発な20代前半がフェロモンの分泌のピークであると言われています。
しかし、これはあくまで一般的な傾向です。年齢を重ねても、心身のバランスが整っている人は、年齢に関係なく魅力的なフェロモンを放つと言われています。よく笑う人、前向きな人、自然体でいる人に魅力を感じるのは、まさに内面の整いが外に「にじみ出ている」からかもしれません。
鍼灸でフェロモンを引き出す「身体づくり」
東洋医学では、「内側の調和が外側にあらわれる」という考え方があります。これは、心身のバランスが整うことで、肌のツヤや血色、そして香りといった「外に出るサイン」も自然に高まる、ということを意味します。
鍼灸治療は、以下のようなアプローチでフェロモンを引き出す身体づくりをサポートします。
- 自律神経の調整: 現代社会で多くの人が抱えるストレスは、自律神経の乱れを引き起こし、ホルモンバランスや体臭にも影響を与えます。鍼灸は、自律神経のバランスを整え、心身のリラックスを促します。
- ホルモンバランスの調整: 鍼灸は、婦人科系疾患や不妊治療において、ホルモン分泌を司る内分泌系に間接的に働きかけ、バランスを整える効果が期待できます。これにより、排卵期のエストロゲン分泌がスムーズになり、フェロモンの表出にも良い影響を与える可能性があります。
- 気血津液の巡り改善: 東洋医学の根幹である「気(生命エネルギー)」「血(血液)」「津液(体液)」の巡りを整えることで、身体全体の機能が高まります。これにより、皮膚の状態が改善され、健康的な体臭が促されます。
「フェロモン」という言葉には特別なイメージがあるかもしれませんが、実は「整った身体と心」こそが、その人本来の魅力を最大限に引き出す、最高の「フェロモン」と言えるでしょう。
妊活中の方も、そうでない方も、日々の生活習慣を見直し、鍼灸を上手に取り入れることで、内側から輝く魅力的な身体づくりを目指しませんか?
ご自身の魅力を最大限に引き出し、心身ともに健やかな毎日を送るために、何かお困りのことがあれば、いつでもご相談ください。


📚参考文献
- Shaw LJ.Emotional processing of natural visual images in brief exposures and compound stimuli: fMRI and behavioural studies.博士論文(PhD). ブルネル大学(英国); 2008年.
- Miller GF. How Mate Choice Shaped Human Nature: A Review of Sexual Selection and Human Evolution. In: Crawford C, Krebs DL, editors. Handbook of Evolutionary Psychology: Ideas, Issues, and Applications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates; 1998. p.87–130. Available from:
ミネラルってなに?五大栄養素のひとつとしての大切な役割
ミネラルってなに?五大栄養素のひとつとしての大切な役割
妊活中の方、体質改善をしたい方にこそ知っておいてほしい「ミネラル」と「五大栄養素」のお話を、根拠に基づいてわかりやすく解説します🧠✨
🌱五大栄養素とは?
五大栄養素とは、私たちの身体をつくり、動かし、整えるために欠かせない栄養素の総称です。以下の5つが含まれます。
- 糖質(炭水化物)
体や脳を動かすエネルギー源 - 脂質
細胞膜・ホルモンの材料。エネルギー源としても重要 - たんぱく質
筋肉、臓器、酵素、ホルモンなど身体の構成要素 - ビタミン
代謝を助け、身体の機能調整をサポート - ミネラル
骨・歯の構成、神経や筋肉の調整、体内環境の維持
🧂ミネラルとは?
ミネラルは体内で合成できないため、食事からの摂取が必須の栄養素です。五大栄養素の中でも特に「身体を整える」働きが強く、少量でも生命維持に重要な役割を果たします。
ミネラルの種類と主な働き
- カルシウム(Ca)
骨や歯の形成、神経伝達、筋肉収縮 - リン(P)
骨・歯の成分、エネルギー代謝の補助 - マグネシウム(Mg)
酵素の働きを助ける、筋肉と神経の調整 - ナトリウム(Na)
血圧や水分バランスの調整、神経の伝達/li> - カリウム(K)
細胞の浸透圧調整、血圧の調節、筋肉の動き - 鉄(Fe)
ヘモグロビンの構成成分、酸素運搬 - 亜鉛(Zn)
免疫機能、味覚、妊娠・出産・成長に関与 - 銅(Cu)
鉄の代謝、酵素の活性化 - マンガン(Mn)
骨の形成、エネルギー代謝 - ヨウ素(I)
甲状腺ホルモンの構成要素 - セレン(Se)
抗酸化作用、免疫サポート - クロム(Cr)
糖代謝、インスリン作用の補助 - モリブデン(Mo)
酵素の補因子として働く
🌸妊活や体質改善においてなぜ大切?
ミネラルや五大栄養素が不足すると…
- ホルモンバランスの乱れ
- 排卵障害・月経不順
- 着床環境の悪化
- 疲れやすさ・冷え・むくみ
- 精神的な不安定さ
といった、不妊の原因や妊娠しづらい体質につながってしまいます。特に亜鉛、鉄、マグネシウムは、妊活中の女性にとって意識したいミネラルです。
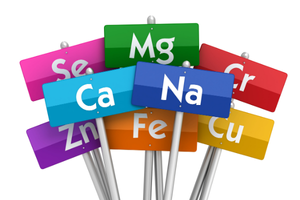
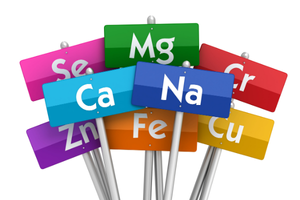
📝参考文献
- ・厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
- ・Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D, National Academies Press, 2011.
- ・WHO. Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition, 2nd edition, 2004.
関連記事
胚盤胞まで育たない原因は栄養不足が原因かも?
胚盤胞にならない…もしかしたら「栄養不足」かもしれません
体外受精において「胚盤胞にならない」「胚盤胞が育たない」と悩まれている方はとても多くいらっしゃいます。複数回の採卵でも胚盤胞まで育たず、「もう無理なのかも…」「私の身体がどこか悪いの?」と落ち込まれてしまう方も少なくありません。
ですが、その背景には見えない栄養不足関係していることもあるのです。
一見健康そうに見える方でも…実は栄養不足
当院でも、痩せ型の方や一見標準体型の方であっても、慢性的な栄養不足が胚盤胞に育たない原因の一つになっているケースをよく見かけます。
中でも注目すべきなのが「コレステロール値の低さ」。「コレステロールは低いほうが健康にいい」と思われがちですが、妊活中はむしろ少し高めの方が良い場合もあるのです。
コレステロール=悪者ではない?妊活中は「材料」に
コレステロールには、妊活において次のような大事な役割があります。
- 卵子の細胞膜の材料になる
- 性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロンなど)の材料になる
- ホルモン分泌や卵胞成熟、胚発育などの生殖機能全体に関与する
つまり、コレステロールが不足すると、卵子の成長に必要な“材料”が足りなくなるのです。これは特に低BMI(痩せ型)の女性に多く見られ、ホルモンバランスが崩れやすくなり、胚の発育にも影響します。
どうしたら胚盤胞が育ちやすくなるの?
大切なのは、「材料をしっかり身体に届けること」。特に意識したいのが以下の2点です。
- タンパク質をしっかり摂ること
- 筋肉を動かして、身体をつくること
筋肉を動かすことでコレステロールやリン脂質の合成が活性化し、血流も良くなります。その結果、卵巣や子宮への血流も安定し、胚が育ちやすい身体へと近づいていくのです。
鍼灸でのサポートも効果的
鍼灸には、自律神経を整えホルモン分泌を促す作用や、骨盤内の血流改善効果が期待できます。実際に、鍼灸と栄養改善を並行して行った方で「初めて胚盤胞まで育った」というケースもあります。“身体づくり”を見直すことが、次の一歩につながる大きなきっかけになるかもしれません。
まとめ
- 胚盤胞が育たない原因のひとつに栄養不足・低コレステロールがある
- コレステロールは卵子やホルモンの重要な材料
- タンパク質摂取・筋肉の維持で材料を整え、血流もアップ
- 鍼灸による体質改善も併せて行うことで、効果的な妊活サポートに


参考文献
Chavarro JE et al. (2008). Protein intake and ovulatory infertility. Human Reproduction, 23(4), 865–872.
関連記事
妊活中に必要なタンパク質と摂り方のポイント
妊活や妊娠中の栄養で「たんぱく質」が大切、という話はよく聞くけれど…「実際どのくらい摂ればいいの?」「プロテインって飲んでもいいの?」そんな疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
今回は、妊活と妊娠におけるタンパク質の役割と、プロテイン選びの注意点を、最新の研究も交えてわかりやすく解説します。
タンパク質は「妊娠の土台」になる栄養素
たんぱく質は、筋肉・内臓・ホルモン・酵素など、身体をつくるすべての材料。特に妊娠を希望する女性にとっては、以下のような点で欠かせません。
- 女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の材料
- 卵子や子宮内膜の質を左右する
- 着床・妊娠維持にかかわる免疫バランスにも関与
- 妊娠中は胎児の筋肉・血液・臓器の発育に必要
厚生労働省の『妊娠前からはじめる妊産婦のための食生活指針』でも、「肉・魚・卵・大豆製品を組み合わせて、たんぱく質を十分に摂る」ことが明記されています。
1日にどれくらいのたんぱく質が必要?
一般的には、体重1kgあたり1.0~1.2gのたんぱく質が推奨されています。例えば、体重50kgの方なら、50~60g/日が目安。ただし、1回の食事で吸収できるのは20〜30g程度とされており、朝・昼・夜と分けて摂ることが大切です。
プロテインは必要?どれを選べばいい?
基本は“食事から”が原則!
まずは、肉・魚・卵・大豆製品などの食材でたんぱく質をしっかり摂るのが理想的です。でも…
- 食事が不規則な方
- 食が細い方
- 妊娠中で必要量が増える方
などは、補助的にプロテインを活用するのもおすすめです。
プロテインの種類と注意点
ホエイプロテイン(乳清)
特徴:吸収が早く、筋肉にも◎
向いている人:妊活中の男女、運動習慣のある人
ソイプロテイン(大豆)
特徴:吸収がゆるやか、女性ホルモン様作用あり
向いている人:妊活中の女性(ただし注意点あり)
【要注意】男性はソイプロテインの摂りすぎに注意!
ハーバード大学のChavarroらによる2008年の研究では、ソイ食品の摂取量が多い男性ほど、精子濃度が有意に低下することが示されました。この研究では、ソイ食品を1日あたり半食分(豆乳1カップなど)摂っていた男性の精子濃度が、摂取しない男性よりも平均4100万/ml少なかったという衝撃の結果が報告されています。特に、過体重または肥満の男性では影響が強く出る可能性があるとも言われています。
つまり、妊活中の男性はホエイプロテインを選んだほうが安心といえます。
まとめ
たんぱく質は妊娠の土台になる栄養で、基本は食事でしっかり摂りましょう。不足時は、無添加・信頼できるプロテインを補助に。男性はソイプロテインに注意(精子数への影響が示唆)しましょう。


参考文献
- 【Chavarro et al.,Human Reproduction,2008】
関連記事
妊活中に激しい運動は大丈夫?女性の卵子の質と運動の関係
「妊活中だからこそ運動をして体を整えたい!」と思う方は多いですが、実は運動のしすぎは卵子の質やホルモンバランスに悪影響を与えることがあります。
本記事では、妊活中の女性に向けて「運動と卵子の質の関係」「妊娠可能期の運動は安全か?」を、最新の研究をもとにわかりやすく解説します。
エネルギー利用可能性(EA)とは?
妊活中の運動を考えるうえで重要なのがエネルギー利用可能性(EA: Energy Availability)です。
EA = 摂取エネルギー - 運動で消費したエネルギー
つまり、運動をした後に体の働きを維持するために残るエネルギーのことを指します。
- EAが十分 → ホルモンバランスが整い、生殖機能や骨密度、免疫機能も正常に働く
- EAが低下(エネルギー不足) → 脳が「繁殖は後回し」と判断し、生殖機能を抑制する
EAが慢性的に不足すると、
- 月経不順や排卵障害
- 卵子の質の低下
- 着床しづらい子宮環境
などにつながるリスクがあります。
運動は卵子の質にどう影響する?
適度な運動は血流改善やホルモンの安定に役立ち、卵巣に酸素や栄養が行き渡りやすくなります。その結果、卵子の質を保つサポートになります。
しかし、過度な運動でEAが不足すると、
- エストロゲン分泌が減少し卵胞発育が不十分になる
- 視床下部性無月経により排卵が止まる
- 黄体機能不全で着床しづらくなる
といった影響が生じることがあります。つまり、「運動=良い」ではなく、「適度」が重要なのです。
妊娠可能期(排卵期〜高温期)の運動は?
「妊娠の可能性がある時期に運動をしていいの?」という疑問はとても大切です。
排卵期の運動
- 軽いウォーキングやストレッチ → 血流を促進し、排卵や受精にプラス
- 長時間のランニングや無酸素系の激しい筋トレ → 卵胞発育やホルモンに悪影響を及ぼす可能性
高温期(排卵後〜生理前)の運動
- 着床の準備をしている大切な時期
- 激しい運動は体温上昇や子宮環境に負担をかける可能性
- ヨガやストレッチなどリラックス効果のある運動が安心
研究でも、軽度〜中等度の運動は妊娠率を高める可能性がある一方で、過度な運動は妊娠率を下げることが報告されています。
女性特有のリスク:女性アスリートの三主徴
過剰な運動と食事制限が重なると、女性には「女性アスリートの三主徴」と呼ばれる症状が現れやすくなります。
- 低EA(エネルギー不足)
- 無月経
- 骨密度低下(骨粗鬆症)
これはアスリートに限らず、一般の女性でも起こる可能性があり、将来的な妊娠力低下につながるため注意が必要です。
妊活中におすすめの運動
◎ 取り入れたい運動
- ウォーキング(20〜30分/日):血流改善・基礎代謝UP
- ヨガ:自律神経を整え、ストレスを軽減
- ストレッチ:骨盤周りの血流改善
× 控えたい運動
- マラソンや長距離ランニング
- ハードな筋トレ
- サイクリング(骨盤周囲の温度上昇に注意)
まとめ
妊活中の女性にとって、運動は「体を整える味方」にも「卵子の質を損なうリスク」にもなりえます。
- エネルギー利用可能性(EA)を意識することが重要
- 卵子の質を守るには、適度な運動+十分な栄養+休養が必須
- 妊娠可能期は、激しい運動を避け、ウォーキングやヨガなどで血流を整える
「頑張りすぎない運動習慣」が、妊娠への近道になります。
📚参考文献
- Loucks AB. (2007). Energy availability and infertility. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes, 14(6), 470–476.
- De Souza MJ, et al. (2014). Hypothalamic amenorrhea in athletes. Semin Reprod Med, 32(6), 433–441.
- Wise LA, et al. (2012). Physical activity and fertility in women: prospective study. BMJ, 345, e4978.


妊娠しやすい身体づくりを始めませんか?
宇都宮鍼灸良導絡院は、大阪市都島区にある妊活専門の鍼灸院です。体質改善から不妊治療のサポートまで、患者様一人ひとりに合わせた施術をご提供しています。妊活や体調のお悩みなど、どうぞお気軽にご相談ください🍀